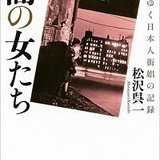匿名さん
東京オリンピックを契機に風俗街一斉浄化の動きがあるのではないか、マイナンバー制度が本格運用されるにあたって周囲にバレたくない風俗嬢は仕事を続けにくくなるのではないか──、風俗街をめぐる状況は日々激しく変化し続けているわけだが、そんな移り変わりの多い夜の街のなかで、いままさに姿を消そうとしている人たちがいる。「街娼」、特に日本人の街娼である。 戦後の混乱期には総数で10万人以上いたと推計される日本人の街娼たちは、それから時を経るなかで徐々に数を減らし、いま街角に立っている少数の人たちのほとんども外国人。日本人の街娼は高齢化も進んでおり、60代70代ですら珍しくない。このままそう時を待たず消滅していってしまうだろう。そんな日本人街娼たちにインタビューを試み、その文化を記録した書籍が最近出版され、話題を呼んでいる。松沢呉一『闇の女たち 消えゆく日本人街娼の記録』(新潮社)だ。同書には、21世紀以降も街に立ち続けている10人以上の人たちによる貴重な証言が残されている。 一筋縄ではいかない人生を歩んだ彼女らの言葉は、もうそれだけで小説や映画の題材にもなりそうなエピソードに溢れている。まず印象的なのが、その「強さ」「豪快さ」を伝える逸話だ。渋谷に立つ55歳の女性は、売春を始めたきっかけをこう語る。 「ルーレットにハマってしまってね。博打が好きで、三十歳までにつぎ込んだお金が二千八百万」 借金で首が回らなくなり売春を始めた後も、ギャンブル癖はおさまらなかった。しかし、すごいのは使った金額だ。結局、ルーレットに1億円近く使ったそうだが、それは当時それだけ儲かった、日本自体が元気のあった時代ということを物語るエピソードでもある。 「当時、この仕事は儲かっていたのよ。一日で三十万とか四十万だってザラだったもの。多い時はもっと稼いだことだってある。信じられないかもしれないけど、マジな話なの。この仕事は日銭でしょ。また明日稼げばいいと思うから、全部使っちゃう」 このような豪快な逸話は他の人のインタビューにも出てくる。広島の46歳の女性もまた「億は使うとるじゃろ」と語る。彼女が大金を使ったのは、「男」だった。ヤクザ者との恋の多かった彼女はこう語る。 「男に使わず、貯めようと思って貯めるじゃろ。でも、また男に惚れて全部使う。六番目の男は知りおうて、三日目に百万ぽんとあげた。"借金がある"って言うから、"返しんさい。ナンボあるの?""百万じゃ""ええよ"って。そのあともどれだけ突っ込んだか」 まさに映画のようである。街に立つ女性たちはこんなにもたくましく豪快なのであった。 しかし、それもかつての話。性風俗産業の変化や、風営法改正などによる繁華街の衰退、日本全体の不景気などの要因が絡み合い、つらく悲しい思いをしている街娼も多くいる。別府に立つ61歳の女性は、基本は客引きをしつつも、自分でも客もとっており、身体を売るその額がわずか500円であることから地元では「500円おばあちゃん」と呼ばれていた。彼女には家がない。客がつかなかった日は公園で寝泊まりしていると言う。そんな彼女は地元の住人からこんな扱いまで受けていた。 「たまに暴走族が来て、髪の毛を引っ張られたり、蹴られたりする。二、三カ月前にも女に木刀で殴られて、民家に逃げた。昔は置屋が金を払っているヤクザがポン引きさんを守ってくれとったですよ。ポン引きはヤクザにお金は払わん。置屋がまとめて払う。そういう人がおったら、暴走族も来ないし、来ても逃げたですよ」 本当にひどい話である。しかしそんな思いをしてまで、なぜ彼女は街に立ち続けるのか。お金を稼がなくては生きていけないから。それはもちろんある。ただ、それだけではない。 地域にもよるが、街娼に新規の客というのはあまりいない。ほとんどは馴染みの客である。その馴染みの客との人間関係が、彼女たちにとってある種の救いとなっている側面もあるのだ。 「楽しかった思い出と言えば、お客さんと飲みに行ってカラオケしたりな、今でも時々お酒につき合うだけでお金をくれる人もおるしな。"あんたは、今日は験がついたんか、ついてないんだったら、コーヒーでもなんでも奢ろうか"ってな」 札幌で街娼をしている50代の女性も同じことを言っている。ここで交わされているのもまた、セックスだけのやり取りではない。 「人と人だからさ。何回か通ってくれれば、いろんな会話をするし、情も通うし。でも、そういう誤解は女の側にもあるからね。男はやればいいと思い込んでいる。そういう女は馴染みを作ろうなんて思わないから、この仕事の面白さに気づかない」 「いろんな人がいて、いろんな話を聞いて、相手のこともだんだんわかるようになってくる。それが楽しい」 彼女の馴染みの客のなかには、驚くべきことに20年以上も通い続けてくれている70代の人もいるそうだ。 「あっちもこっちも歳をとって、前は毎週来てくれていたのが月に一回になったり、しばらく来れなくなったりするけど、もうその人たちとは他人じゃないよね」 「七十代の客もちゃんとやっていくよ。"ここ、行くぞ""ここ、行くぞ"って言ってイクんだよ、その人は(笑)」 夜の街に何十年と立ち続けるには、それ相応に強くなければならないし、否が応でも強くならざるを得ない。この札幌の路上に立つ女性は、なんと、おとり捜査をした警察を相手取り、最高裁まで闘ったこともあるのだと言う。 「本当は"おねえちゃん、なんかいいことない?"って声をあちらからかけちゃいけないんだよ。おとり捜査だから。今は生活安全課だけど、その当時は保安課と言って、その保安課の一番偉いのが、若いのを二人連れてきて、"オレのやり方を見てろ"ってなもんでさ。なんとか捕まえたかったわけよ」 「でも、みんなわかるわけよ。怪しいって。誰も声をかけてこないから、焦って自分から声をかけたんだろうね。それでは捕まらないと思っているから、こっちは値段もホテルも言ったら、"警察だ"って言うわけよ」 この捜査のやり方に疑問をもった彼女は最高裁まで争う。結局は、売春目的で客待ちをしていたこと自体が売春防止法第五条違反とされ、罰金6000円で刑が確定するのだが、おとなしく泣き寝入りぜずに徹底的に闘い続けたその姿勢は、組織に頼らず、ひとり街に立って生き続けてきた強さとつながっている気がする。 『闇の女たち』におさめられたインタビューのなかには、数年前すでに松沢氏のメルマガなどに掲載されているものもある。なので、改めて書籍におさめる確認をとると同時に、掲載料を払おうと思い、何人かに再度コンタクトをとろうとしたが、もう誰一人として会うことはできなかったと松沢氏は言う。 日本人の街娼たちはこうして消滅しようとしている。本書に掲載された証言は遠くない未来、かつて日本に存在した人々を記録した資料として貴重なものとなるのかもしれない。500円で体売る61歳、公園で野宿も…街角に立ち客をとる女性たちの人生 - ライブドアニュース
新潮社から「闇の女たち 消えゆく日本人街娼の記録」が出版された。21世紀以降も街に立ち続けている10人以上の貴重な証言が残されている。別府に立つ61歳の女性は500円で体を売り、公園で寝泊まりしているという